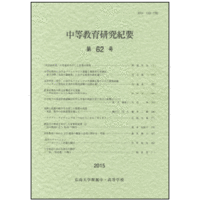
この文献の参照には次のURLをご利用ください : https://doi.org/10.15027/50504
中等教育研究紀要 67 号
2021-03-31 発行
「論理国語」における言語活動を取り入れた授業提案 : 『「である」ことと「する」こと』(丸山真男)の場合
Class Proposals that Incorporate Language Activities in "Japanese Language(Logic)": A case of "To be" and "To do"(by Masao Maruyama)
Abstract
高等学校学習指導要領(平成三十年告示)で新しく設置される選択科目「論理国語」では、「書くこと」に三割から四割強配当するよう明示されている。『「である」ことと「する」こと』(丸山真男)を使って、どのような「読むこと」「書くこと」の指導過程をとることで、効率よく「書く」力は高まっていくのかを考察した。「である」論理と「する」論理で現代社会を分析する文章を書かせた結果、以下の四つが提案できた。
① 自分の問題として受け止められるような書くテーマを設定する。
② 構成メモを使って、思考の枠組みを作成した後、生徒同士の相互批評を行う過程を踏んで、文章を書く。
③ 「接続詞」の働きを取り上げたレッスンを組み入れる。
④ 評価の観点を簡略化し、文章を評価してすぐ返却し、かつ文章を多く書く機会を設ける。
① 自分の問題として受け止められるような書くテーマを設定する。
② 構成メモを使って、思考の枠組みを作成した後、生徒同士の相互批評を行う過程を踏んで、文章を書く。
③ 「接続詞」の働きを取り上げたレッスンを組み入れる。
④ 評価の観点を簡略化し、文章を評価してすぐ返却し、かつ文章を多く書く機会を設ける。
Abstract
New Course of Study for High Schools(2019)clearly states that "Japanese Language(Logic)" should assign about 30% to 40% of total teaching hours to "writing" . What kind of "reading" and "writing" instruction process will be followed by using "To be" and "To do"(by Masao Maruyama)to efficiently improve "writing" ability?
As a result of having them write an essay that analyze modern society with the logic of "To be" and "To do": the following four proposals were made:
① Select a writing theme which is closely related to yourself.
② After creating a framework using the composition memo, students discuss and criticize the text "To be" and "To do" in pairs and then write an essay.
③ Incorporate lessons that deal with the function of "conjunctions".
④ Simplify the viewpoint of evaluation, evaluate sentences and return them immediately, and provide an opportunity to write many essays.
As a result of having them write an essay that analyze modern society with the logic of "To be" and "To do": the following four proposals were made:
① Select a writing theme which is closely related to yourself.
② After creating a framework using the composition memo, students discuss and criticize the text "To be" and "To do" in pairs and then write an essay.
③ Incorporate lessons that deal with the function of "conjunctions".
④ Simplify the viewpoint of evaluation, evaluate sentences and return them immediately, and provide an opportunity to write many essays.
About This Article
Other Article
PP. 21 - 38