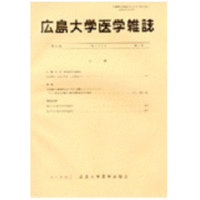
この文献の参照には次のURLをご利用ください : https://doi.org/10.15027/786
広島大学医学雑誌 49 巻 4/5 号
2001-10-28 発行
数式化によって3次元測定から手舟状骨の形態を評価する試み <原著>
A Morphological Study of the Scaphoid Bone using a Mathematical Technique and Three-Dimensional Measurements
福田 祥二
Abstract
As scaphoid fracture can be largely asymptomatic, diagnosis is often made after nonunion has already occurred. In order to properly treat scaphoid nonunion, precise reconstructive surgery is necessary. For this purpose, full-scale modeling of the scaphoid bone was attempted, utilizing data from 3D CT images. Data was directly measured from scaphoid bones using 51 hands removed from 40 cadavers, and derived from 3D CT images using 10 of the 51 hands. The resulting solid models of the regeneration curve, calculated using median data from the 51 scaphoid bones, seemed appropriate for clinical application as a standard of reconstruction in operations for scaphoid fracture. The model produced from 3D CT images more closely approximated physical measurements if the magnifying rate of the measurement system underwent correction. However, some degree of error is inevitable in restructuring independent models of scaphoid bone utilizing this system of image processing with data derived from 3D CT images. At present, the best way to utilize a model is from mirror images of 3D CT images of the other wrist joint, and then to apply this model clinically with due consideration of a certain amount of artifactual expansion.
Abstract
舟状骨骨折は症状が軽度のため, 発見されたときには陳旧例となり, 骨吸収によって正常の形態が崩れていることも少なくない。手術時の整復操作は, 術者の経験に基づいた勘に頼らざるを得ないのが現状である。3D CTからの実物大モデルを再構築することができれば, より正確な治療に結びつくと考えた著者は, 舟状骨の形態計測を行うとともに, 3D CT画像データからの再構築を試みた。本論文は, その基礎データを解析したものである。対象は, 系統解剖用遺体40体(男性23体, 女性17体)の内, 左右対の摘出が11体(男性9体, 女性2体)に可能であったが, 残りの29体は片側のみの摘出となったため, 51手(男性32手, 女性19手), 右27手, 左24手であった。測定には接触型3次元スキャナーを使用した。男女間では, 長軸長に有意差を認め, フーリエ係数には認めなかった。左右では, 長軸長, フーリエ係数ともに有意差を認めなかった。Compsonらの形態分類に従い3型に分類可能であったが, その3型間のフーリエ係数には有意差を認めた。また, 全体, 男女別, 型別に, 各々の中央値を用いて再生曲線を作成した。この曲線を立体モデル化すれば, 舟状骨骨折の手術時に本来の掌側面をどの様に再建すべきかの目安として, 臨床応用が可能と思われた。10手に関しては, 3次元スキャナー計測群, 舟状骨単体の3D CTからの計測群と手関節3D CTから切り出した舟状骨の計測群の長軸長とフーリエ係数の比較検討をおこなった。計測システムの拡大率を補正できれば, 3D CTから作成されるモデルは実際の測定結果に近づくことがわかった。今回の画像処理システムでは, 手関節3D CTから舟状骨のモデルを作成することに関して誤差が大きかった。現状では, 健側手関節3D CT画像の鏡面像から舟状骨を含むモデルを作製し, ある程度の拡大を考慮して臨床応用すべきだと考えた。
About This Article
著者キーワード
Fourier transformation
Morphological study
Scaphoid
Three-Dimensional CT
Other Article
PP. 133 -